何の前触れもなく突如、虚空に出現する「月人」たち。その姿は涅槃来迎図を思わせるが、その振る舞いは破壊神そのもの。不定期に現れる、この”使徒襲来”に立ち向かうのは28体の宝石たち…。
『虫と歌』『25時のバカンス』などで目利きのマンガ読みたちをうならせた市川春子が王道バトルもの(?)を描いてみたら、とんでもないことになってしまった!
作者自らが手掛けたホログラム装丁があまりにも美しい。写真ではちょっとわかりにくいか。ぜひ現物を手に取ってほしい。
(市川春子『宝石の国』講談社)




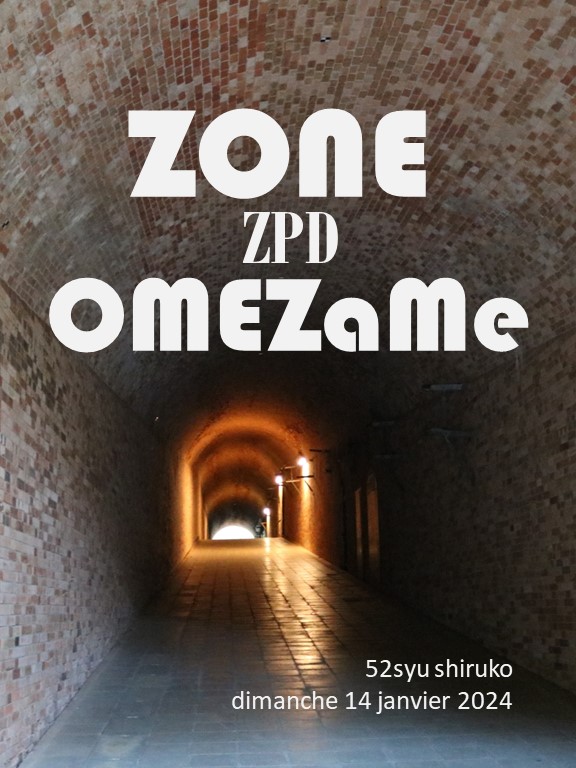
12月30日は何の日だって? 真っ先に思い浮かぶのは「地下鉄記念日」です。昭和2年(1928年)のこの日、上野―浅草間2.2kmを黄色の車両が走ったんですから。当時のポスターには、誇らしげに「東洋唯一の地下鉄道」と文字が躍ってます。
52[守」にとっての12月30日は? バックヤードを覗いてみれば、実は地下鉄開通並みの騒ぎでした。この日、指導陣と師範代が集うラウンジで、1月14日の「本楼合同汁講」に向けて、怒濤の交わし合いが始まったのですから。『地下鉄のザジ』だったら「けつ喰らえ」という大騒ぎです。
大濱朋子師範代から「52守はわたしのもの」と、合同汁講を「自分ごと」として引き受ける宣言が飛び出せば、内村放師範代はすかさずオンラインミーティングを企図、周囲を巻き込んでいきました。開催までに同ラウンジで、138ものやりとりがあったことを付加しておきます。
そうなんです。もひとつ付け加えるなら、12月30日といえば、番ボーも始まり、師範代たちは指南に大忙しだったのです。ですが師範代たちは“開通”に向けて、「汁講プランニング」を止めませんでした。
リアルで集う合同汁講は、午前の部、14時の部、16時の部、と3チームによる別立ての開催になったのですが、16時の部だけは、オンラインとリアルのハイブリッド開催を敢行しました。集まったのは、高田智英子師範代の語部おめざめ教室、水野亜矢師範代の時々ゾーン教室、大濱朋子師範代の白墨ZPD教室の3つ。
北は北海道の水野師範代、南は沖縄の大濱師範代、真ん中の滋賀からは阿曽祐子番匠、本楼には栃木から高田師範代が駆けつけました(高田師範代は、開始4時間前に駆けつけ、準備に余念がありませんでした)。学衆に目を転ずれば、本楼参加3名に加え、他の教室で学ぶ妻も誘って参加した学衆もいれば、アムステルダムや京都からZOOMにアクセスした学衆も。ゲストの平野しのぶ花伝師範、嶋本昌子花伝師範を交えた総勢20名の大所帯となったのです。
▲合同汁講のために福島から駆けつけた鈴木康代学匠(左)、汁講進行を笑顔でリードした高田師範代(中)、テクニカルを一手に引き受けた縁の下の力持ち、阿久津健師範(右)。阿久津師範の奥の画面には、ZOOMに参集した学衆の顔が見える。
少女ザジのパリの2日間を描いたレイモン・クノーの『地下鉄のザジ』(生田耕作訳/中公文庫)には、女装ダンサーのガブリエルおじさんをはじめ、“多様性”という言葉では括れない人々が次々と登場します。しかし考えてみれば、この合同汁講に集った20名は、世間の属性を脇に置いたぶん(ついでに世間のルールも脇に置いたせいで)、『地下鉄のザジ』さながらのごった煮となったのでした。
ごった煮で何ができたかって? 少しだけその成果をご覧に入れましょう。
選本した1冊から教室を見立てる「本で教室見立て」をとっかかりに、本楼参加者が本楼の中から本を1冊選んで、掛け合わせる「本で教室キャッチフレーズ」というワークを行いました。ざっくりまとめれば、参加者は6万冊の本楼をめぐりつつ、本で遊び尽くしたのでした。
これが、出来上がった「キャッチフレーズ」です。
●語部おめざめ教室
『語り芸パースペクティブ』(玉川奈々福編著/晶文社)×『あゝ、荒野』(寺山修司/角川文庫)×『花さき山』(斎藤隆介・作、滝平二郎・絵/岩崎書店)×本楼本『戦国のコミュニケーション』(山田邦明/吉川弘文館)
→ 擬型 千形 桜吹雪
「師範代の声が教室の隅々まで、遠くに近くに響いている」(Oさん)、「この教室は情報を先入観なくフラットに扱ってくれる」(Iさん)、「教室に色んな花が咲いている」(Yさん)という教室見立てから、連想がめざめていった。生まれ出た共通ワードは、花咲く吉野山を縦横無尽に駆け回った「義経」だ。ここから編集が入る。義経を音読みにして、ギケイ。ギケイとは、「擬き(モドキ)」の型。「擬き」の型から、千のカタチとなっていく。学衆と師範代の「語り」は、千の花片になって舞う。桜吹雪だ。「最後にみんなで花を咲かせましょう!」。教室の目指す方向が決まった。(高田智英子師範代)
●時々ゾーン教室
『ぶらんこ乗り』(いしいしんじ/新潮文庫)×『オーデュボンの祈り』(伊坂幸太郎/新潮文庫)×『没後400年 長谷川等伯 特別展覧会図録』(毎日新聞社)×本楼本『百人一酒』(俵万智/文春文庫)
→ 個性を収穫し、思考を醸す 時々ゾーンどぶろく
学衆に酒好きが多数いる。そんな特徴からOYさんが本楼で選んでくれたのが『百人一酒』だったが、「連想シソーラス」すると、お酒の名前、酒場、ブレンド、酒造りと、あっという間に「酒」尽くしになった。OSさんが進行ロールを担い、出てくるアイデアに合いの手を入れ、「型」を差入しつつリードした。そして生まれたのが、「個性を収穫し、思考を醸す」。ビールかウイスキーのCMキャッチコピーのようだ。ラストの詰めで、Tさんが「教室」を「どぶろく」に置き換えた。原料を濾さない「どぶろく」に教室模様を見たのだろう。一気に「日本らしさ」が起爆した。その日参加していない教室仲間の「日本好き」が「ないものフィルター」でアフォードされた。(水野亜矢師範代)
●白墨ZPD教室
『千夜千冊エディション 仏教の源流』(松岡正剛/角川文庫)×『深夜特急』(沢木耕太郎/新潮文庫)×『蟲師』(漆原友紀/講談社)×『フラジャイル』(松岡正剛/ちくま学芸文庫)×本楼本『工芸 日本史小百科』(遠藤元男、竹内淳子/近藤出版社)
→ トンネルの先の白
教室を引っ張ってくれている参加者のAさんから、事後、「たくさんの皆さんが集うと、いろんな感受性に触れ合うことができ、10分位で触発連鎖するんだなと実感した」との声が漏れた。そう、ここは感受性が集う場所。オランダからも千葉からも沖縄からも、誰もが何かを求めやってきた。ここ(教室)は、ワクワクもあるけれど、儚く脆く消えそうで、未完成で不安で痛くもあった。だから「その先」を求める。トンネルの中で苦悶しながら、その暗闇で皆の揺れるプロフィールを重ねながら、深夜特急が夜を駆けるように、「その先」の「白」を目指すのだ。「その先」は2月11日のその向こう。超えた時に私はみんなと一緒にいたい。(大濱朋子師範代)
パリの2日間を終えたザジの元に、母親が迎えに来ます。何をしていたのかと問われたザジはこう答えるのでした。
「年を取ったわ」
パリの2日間は、少女ザジにとって密々で、しかも加速度的な変化の中にありました。そりゃあ年も取ります。ですが、ザジの2日間に勝るとも劣らない濃密な時間の流れが、ここにありました。
ハイブリッドの「本楼合同汁講」は、わずか2時間の出来事でしたが、参加者の誰もが同じ事を思ったはずです。なんて濃いんだ、と。編集によって、時間はいかようにも濃くなるのです。今まで閉じていた連想の扉が開き、お互いの思考が開通し合った時間でした。
そして時々ゾーン教室は思考の発酵へと向かい、語部おめざめ教室は「サクラサク」を目指し、白墨ZPD教室はトンネルの先へと歩き出したのでした。
取材・文/大濱朋子、高田智英子、水野亜矢
構成・文/角山祥道
その先→ ◎第52期[破]応用コース◎
●期間 :2024年4月22日(月)~2024年8月11日(日)
●申込締切 :4月7日(日)
●申込先 :https://es.isis.ne.jp/course/ha
●問い合わせ:isis_editschool@eel.co.jp
イシス編集学校 [守]チーム
編集学校の原風景であり稽古の原郷となる[守]。初めてイシス編集学校と出会う学衆と歩みつづける学匠、番匠、師範、ときどき師範代のチーム。鯉は竜になるか。
花伝所の指導陣が教えてくれた。「自信をもって守へ送り出せる師範代です」と。鍛え抜かれた11名の花伝生と7名の再登板、合計18教室が誕生。自由編集状態へ焦がれる師範代たちと171名の学衆の想いが相互に混じり合い、お題・ […]
これまで松岡正剛校長から服装については何も言われたことがない、と少し照れた顔の着物姿の林頭は、イシス編集学校のために日も夜もついでラウンジを駆け回る3人を本棚劇場に招いた。林頭の手には手書きの色紙が掲げられている。 &n […]
週刊キンダイvol.018 〜編集という大海に、糸を垂らして~
海に舟を出すこと。それは「週刊キンダイ」を始めたときの心持ちと重なる。釣れるかどうかはわからない。だが、竿を握り、ただ糸を落とす。その一投がすべてを変える。 全ては、この一言から始まった。 […]
55[守]で初めて師範を務めた内村放と青井隼人。2人の編集道に[守]学匠の鈴木康代と番匠・阿曽祐子が迫る連載「師範 The談」の最終回はイシスの今後へと話題は広がった。[離]への挑戦や学びを止めない姿勢。さらに話題は松 […]
目が印象的だった。半年前の第86回感門之盟、[破]の出世魚教室名発表で司会を務めたときのことだ。司会にコールされた師範代は緊張の面持ちで、目も合わせぬまま壇上にあがる。真ん中に立ち、すっと顔を上げて、画面を見つめる。ま […]










コメント
1~3件/3件
2025-10-02

何の前触れもなく突如、虚空に出現する「月人」たち。その姿は涅槃来迎図を思わせるが、その振る舞いは破壊神そのもの。不定期に現れる、この”使徒襲来”に立ち向かうのは28体の宝石たち…。
『虫と歌』『25時のバカンス』などで目利きのマンガ読みたちをうならせた市川春子が王道バトルもの(?)を描いてみたら、とんでもないことになってしまった!
作者自らが手掛けたホログラム装丁があまりにも美しい。写真ではちょっとわかりにくいか。ぜひ現物を手に取ってほしい。
(市川春子『宝石の国』講談社)
2025-09-30

♀を巡って壮絶バトルを繰り広げるオンブバッタの♂たち。♀のほうは淡々と、リングのマットに成りきっている。
日を追うごとに活気づく昆虫たちの秋季興行は、今この瞬間にも、あらゆる片隅で無数に決行されている。
2025-09-24

初恋はレモンの味と言われるが、パッションフルーツほど魅惑の芳香と酸味は他にはない(と思っている)。極上の恋の味かも。「情熱」的なフルーツだと思いきや、トケイソウの仲間なのに十字架を背負った果物なのだ。謎めきは果肉の構造にも味わいにも現れる。杏仁豆腐の素を果皮に流し込んで果肉をソース代わりに。激旨だ。