何の前触れもなく突如、虚空に出現する「月人」たち。その姿は涅槃来迎図を思わせるが、その振る舞いは破壊神そのもの。不定期に現れる、この”使徒襲来”に立ち向かうのは28体の宝石たち…。
『虫と歌』『25時のバカンス』などで目利きのマンガ読みたちをうならせた市川春子が王道バトルもの(?)を描いてみたら、とんでもないことになってしまった!
作者自らが手掛けたホログラム装丁があまりにも美しい。写真ではちょっとわかりにくいか。ぜひ現物を手に取ってほしい。
(市川春子『宝石の国』講談社)




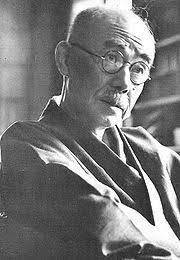
吉村堅樹
僧侶で神父。塾講師でスナックホスト。ガードマンで映画助監督。介護ヘルパーでゲームデバッガー。節操ない転職の果て辿り着いた編集学校。揺らぐことないイシス愛が買われて、2012年から林頭に。
【オツ千ライブ!】本日10/3 22時より『まつりちゃん』をおっかけ!
千夜千冊絶筆篇 1855夜 岩瀬成子『まつりちゃん』をオツ千ライブでおっかけ! 千夜坊主の吉村堅樹と千冊小僧の穂積晴明による「おっかけ千夜千冊ファンクラブ」こと、オツ千!。1855夜 岩瀬成子『まつりちゃん』、オツ千 […]
【オツ千ライブ!】9/25 20時より初のWヘッダー蕪村&ボームをおっかけ!
千夜千冊をおっかけつづけて4年150夜を超えて、初めての二夜をおっかけLIVE開催! 千夜坊主の吉村堅樹と千冊小僧の穂積晴明による「おっかけ千夜千冊ファンクラブ」こと、オツ千!。850夜 与謝蕪村『蕪村全句集』&10 […]
【続報】9/27(土)伝習座 無料生配信! 今福龍太登壇&松岡正剛校話「花綵イシス」
伝へて習はざるか。 千夜千冊996夜 王陽明『伝習録』では、『論語』学而の「伝不習乎」を引いて、「伝習」の意味を説いている。雛鳥が飛び方を学ぶように、人が真似て、何事かに集中していくことが「習」の字には込められている […]
【オツ千ライブ!】9/9 20時より 1854夜 佐藤優『国家論』配信
千夜千冊絶筆篇 1854夜 佐藤優『国家論』をオツ千ライブでおっかけ! 千夜坊主の吉村堅樹と千冊小僧の穂積晴明による「おっかけ千夜千冊ファンクラブ」こと、オツ千!。1854夜 佐藤優『国家論』、オツ千LIVEを9/9 […]
【知の編集工学義疏】第3章 <情報社会と編集技術>のキーワード
今こそ、松岡正剛を反復し、再生する。 それは松岡正剛を再編集することにほかならない。これまでの著作に、新たな補助線を引き、独自の仮説を立てる。 名づけて『知の編集工学義疏』。義とは意見を述べること、疏とは注釈をつけ […]
コメント
1~3件/3件
2025-10-02

何の前触れもなく突如、虚空に出現する「月人」たち。その姿は涅槃来迎図を思わせるが、その振る舞いは破壊神そのもの。不定期に現れる、この”使徒襲来”に立ち向かうのは28体の宝石たち…。
『虫と歌』『25時のバカンス』などで目利きのマンガ読みたちをうならせた市川春子が王道バトルもの(?)を描いてみたら、とんでもないことになってしまった!
作者自らが手掛けたホログラム装丁があまりにも美しい。写真ではちょっとわかりにくいか。ぜひ現物を手に取ってほしい。
(市川春子『宝石の国』講談社)
2025-09-30

♀を巡って壮絶バトルを繰り広げるオンブバッタの♂たち。♀のほうは淡々と、リングのマットに成りきっている。
日を追うごとに活気づく昆虫たちの秋季興行は、今この瞬間にも、あらゆる片隅で無数に決行されている。
2025-09-24

初恋はレモンの味と言われるが、パッションフルーツほど魅惑の芳香と酸味は他にはない(と思っている)。極上の恋の味かも。「情熱」的なフルーツだと思いきや、トケイソウの仲間なのに十字架を背負った果物なのだ。謎めきは果肉の構造にも味わいにも現れる。杏仁豆腐の素を果皮に流し込んで果肉をソース代わりに。激旨だ。